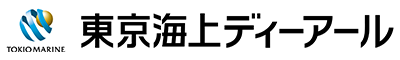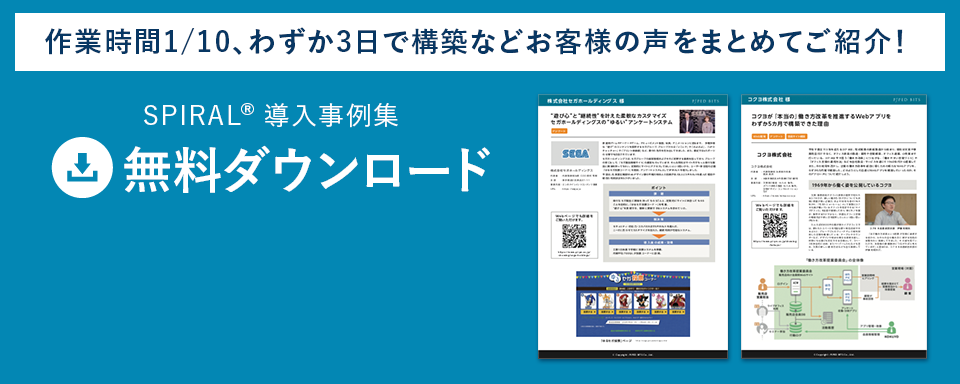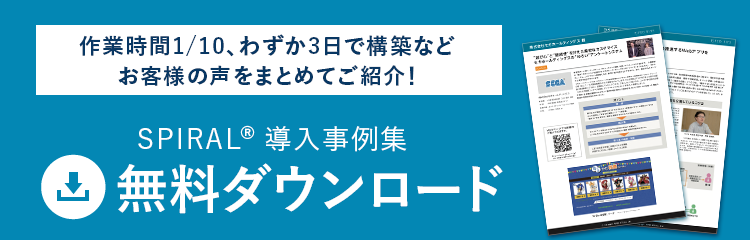講座への参加申し込みをメールやExcelで管理しており、
手間のかかるアナログ作業から脱却したかった
SPIRAL® 導入の背景をお聞かせください。
地方自治体からの業務委託で開催するBCP策定講座では、2年前に、それまでのFAX受付方式から、Excelの帳票をメールで送付いただく形式に変更いたしましたが、それでも、管理に多くの手間と時間が掛かっていました。
1枚のシートに必要なすべての項目(企業名、役職名、氏名、連絡先、希望日等)をまとめたExcelのテンプレートを弊社で用意し、参加希望の企業に必要項目を記入いただきメールでご提出いただくという流れです。
その後、弊社でメールと帳票を確認したのち、担当者が弊社内のデータベースに転記していました。当然、他の通常業務に取り組みながらの追加業務でしたので、かなりの作業時間が講座の受付業務に割かれていたことは否定できません。
作業時間や手間以外には、どのような課題があったのでしょうか。
リアルタイムに参加企業が把握できていなかったことが挙げられます。参加希望メールは目視で確認し、転記していたため、メールが届いてからデータベースが更新されるまでタイムラグがありました。
また、キャンセルや登録情報の変更といった修正依頼があった場合も、データベースを更新する必要があります。そのため、参加企業の一覧が必要になった場合、最新の情報が反映されているかどうか、データベースの情報を一つひとつ確認する手間が発生していたのです。
Webからの参加申し込みができる仕組みは、以前から検討されていたのでしょうか。
FAXからExcelに変更したことは、一歩前進でしたが、世の中を見渡してみると、セミナーの申し込みはWeb申込が一般的になっていると感じていました。そんな時、ある協会から依頼があり、災害対応ワークショップ訓練の講師としてその協会を訪ねた際、Webから申し込めるSPIRAL® の存在を知り、これを弊社でも導入したいと思ったのです。
しかし、SPIRAL® を導入するためには、社内の厳しいセキュリティ基準をクリアする必要がありました。Web上で参加企業に情報を入力してもらい、そのデータをSPIRAL® 内に保存するには、個人情報保護の観点で、SPIRAL® のセキュリティ管理状況を慎重に確認しなければなりませんでした。
厳しいセキュリティチェック審査に合格したSPIRAL® で、
講座のWeb受付を実現。フォームによる申し込みの受付、
参加企業へのメール送付も自動化
厳しいセキュリティチェック審査をどのようにクリアしたのですか。
数か月に及ぶ厳しいセキュリティチェック審査を実施することになりましたが、東京海上グループにおける厳しい審査基準に照らしたチェック項目に一つ一つ回答していただいたことにより、SPIRAL® の安全性が確認され、講座のWeb受付を開始できるようになりました。
導入の時点で、SPIRAL® をどのように感じておられましたか。
私は、以前、大手情報通信系企業の人事部門で勤務していたという背景もあり、1990年代に起きたパラダイムシフトを思い出しました。当時「ネオダマ」という言葉がありました。ネットワーク化、オープン化、ダウンサイジング化、マルチメディア化という大きな変革の流れを象徴する言葉です。プログラミング言語が分からない人間でも、SPIRAL® を使えば自社に必要なシステムを組める。この20数年の間に、ここまで進化したのかと、驚きとともに感動さえ覚えました。
実際にパイプドビッツ社のご担当者にアドバイスいただきながら操作すると「あぁ、こんなことまでできるんだ」と驚きの連続でした。そうした意味で、SPIRAL® は時代の最先端をいく、無限の可能性を秘めたインフラとしての存在価値があるなと思います。
SPIRAL® 導入の流れをお聞かせください。
地方自治体の公募・入札があり、一年間の講座スケジュールが固まり始める2021年4月中旬頃に、ちょうどSPIRAL® の社内セキュリティ審査が完了したとの連絡がありました。ほぼ同時期に地方自治体の案件実施が決まりました。
非常にタイトなスケジュールでしたが、ご担当者のキメ細かいご支援にも支えられ、何とかセミナー受付システムを完成することができました。例えば、SPIRAL® の基本仕様では、参加者単位の管理となりますが、ある地方自治体の案件では、参加企業数の目標を定めてあったため、参加者単位ではなく会社単位での管理ができるよう、データベースの構成を工夫したりしました。
具体的な講座の内容としては、BCPの普及啓発セミナーや自然災害や新型感染症を対象とするBCP策定セミナーなどを実施しています。1回の講座に20〜50社、累計で1年間に300〜400社に参加いただいた計算です。
今回のシステムを構築する上で工夫したポイントはありますか。
参加申し込みの際には、連絡漏れがないようにメールアドレスを二つ(メインとサブ)記載していただくことにしておりましたが、お申込み後に自動で送信されるサンクスメールも、メインとサブの両方に自動送信されるように工夫しました。
また、地方自治体からの要望でどの業界の企業が、どのくらい参加していたかをすぐに分析できるよう、企業ごとに業種コードを振り分けたことも工夫の1つです。

講座参加受付が自動化されたことで、チェック作業も不要に。
参加者をリスト化して効率的なアフターフォローも実現!
SPIRAL® の導入で、社外からはどのような評価がありましたか。
SPIRAL® を導入したことで「スマホやPCを使って、Web上から参加申し込みができる」ということは地方自治体へ提出した提案書のなかに盛り込んでおり、申し込みに手間が掛からず簡単であることをメリットとして訴求していました。地方自治体の職員の方に申し込みフォームについて説明した際に「最先端の仕組みなのですね」との感想を頂いています。
社内の業務には、どのような変化がありましたか。
Web上で24時間、参加受付ができるようになったことで、リアルタイムで参加申込情報がデータベースに更新されるようになりました。以前のように、FAXやExcelで受け付けていた時には、届く情報を転記する作業が必要(そのための残業もかなりあった)でしたが、これが一切なくなりました。地方自治体への定期報告に必要な参加企業の名簿も、SPIRAL® からダウンロードするだけで作成でき、とてもスムーズになっています。
さらに、講座実施直前のリマインドメールが効率化されたことも大きいです。以前の方法では、Excelから対象者のメールアドレスを手作業で抜き出し、送信ミスがないようにBCCでお送りしていました。手作業ではどうしてもミスが発生するので、送信前にはダブルチェックが必要でした。SPIRAL® のおかげで、安心してメール送信ができるようになっています。

今後の展望についてお聞かせください。
地震、風水害、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、緊急事態における事業継続計画を策定しなければならない企業は、今後さらに増えてくるでしょう。大企業ではかなり浸透してきましたが、やはり地方の中小企業はまだまだ策定率が低いのが実情です。
新型コロナウイルス感染症対応の一環として、オンラインセミナーも普及してまいりました。東京に居ながらにして、全国の企業に募集を呼びかけ、申込を受けつけ、名簿を作成し、資料を送付して、セミナーを実施する。このような一連の業務は、信頼できるシステムがなければ、とても安心して実施できるものではありません。
そのためのプラットフォームを提供するのが、SPIRAL® であり、一言で例えるなら「安心して大海に漕ぎ出せる船」のような存在だと感じています。
今後も様々なニーズにお応えして、様々なセミナーを実施していく予定です。
引き続きSPIRAL® を活用していきたいですね。